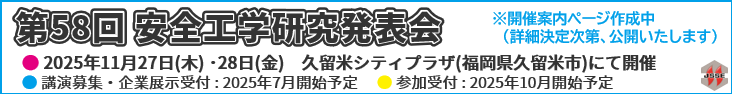セーフティー・はーと
セーフティー・はーと
第41号
高木伸夫 <システム安全研究所>
企業モラルが問われて久しくなる。最近でも多くの不祥事が相次いでいる。化学プラント、鉄道、電力など社会を構成する多様な産業の安全確保にあたってその基本となるのが企業安全理念である。
企業モラルが問われて久しくなる。最近でも多くの不祥事が相次いでいる。化学プラント、鉄道、電力など社会を構成する多様な産業の安全確保にあたってその基本となるのが企業安全理念である。
企業のトップマネジメントによる安全理念は企業が社会との共生を保つための規範を示すものであり、また、安全確保にあたっての根幹をなすものといえる。企業安全理念の欠如は安全確保にあたっての従業員の意識向上を期待できず、その結果、事故予防にあたってのインセンティブが与えられない。安全とよく管理された操業の間には明らかな関係があるといわれており、安全理念のもとに事故予防にあたって財政面ならびに人材面から適切な資源を投入する必要がある。企業のトップマネジメントは生産性のみを追及せず、自らのリーダーシップのもと安全に対するコミットメントを出し、それを受けたすべての従業員が安全理念を理解しボトムアップからの安全活動を実践するという文化の確立が重要である。安全の確保は企業の社会的使命であるとともに責務でもあるという基本に立ち返って企業安全理念の確立と浸透を図ることを期待する。Safety is a good businessというではありませんか。
第40号 韓国邸丘の地下鉄惨事に想う(その1 桜木町駅電車炎上事故)
坂 清次 (株)三菱総合研究所 客員研究員
2月18日に韓国の邸丘で起きた地下鉄放火事故は、死者が200人以上と空前の惨事となった。先行の事故車両の被害より、後から駅に進入してきた対向車両で大半の死者が出るということになり、放火犯に加え、事故車と対向車の運転士、運行司令室と火災警報の設置された設備司令室の地下鉄関係者7名に逮捕状が出ている(3月12日現在)。
2月18日に韓国の邸丘で起きた地下鉄放火事故は、死者が200人以上と空前の惨事となった。先行の事故車両の被害より、後から駅に進入してきた対向車両で大半の死者が出るということになり、放火犯に加え、事故車と対向車の運転士、運行司令室と火災警報の設置された設備司令室の地下鉄関係者7名に逮捕状が出ている(3月12日現在)。
当事者の状況認識の甘さと関係者間の総合的な(場の)認識が共有されていないことが最大要因であり、また事故後の隠蔽工作など問題点が多いが、ここでは経験の浅い地下鉄公社の組織としての危機管理能力について書いてみる。1997年に営業運転を開始しているが、いきなりワンマン運転で遠隔指令という最新の自動化システムでスタートしていることに鍵がありそうである。火災警報機をいつものことだと無視し、運転士に的確に指示も情報も出せていないが、これから次々と事実が明らかにされよう。乗客も非常コックを開けていないようである。
そこで私たちの知っている桜木町事故に触れたい。戦後間もない1951年4月24日13:43に起きた、国電桜木町駅構内での電車火災事故である。工事ミスで垂れ下がった吊架線に、進入してきた電車のパンタグラフが絡んだため放電し木造の車両が炎上したが、窓が3段式で人が出られず、106名が車内で焼死したものである。この事故を契機に、不燃化や非常コックなどの保安対策がとられるようになったものである。現場は安全工学協会からほど近い高架部分である。実はこの3日後に上信電鉄で同様の事故が起きたが、幸い被害は軽かった。
ご安全に
第39号 第18期学術会議安全工学専門委員会報告書
小川輝繁 <横浜国立大学大学院工学研究院>
本年は学術会議の18期と19期の変わり目の年です。そこで、第18期安全工学専門委員会(委員長 菅原進一東京大学大学院教授)の報告書を作成しています。
本年は学術会議の18期と19期の変わり目の年です。そこで、第18期安全工学専門委員会(委員長 菅原進一東京大学大学院教授)の報告書を作成しています。
本セーフティ・ハートでも取り上げられているようにテロ、薬害、遺伝子組み換えによる食糧生産の潜在危険など一般市民が不安を抱いている問題が増えています。そこで、今期のテーマは「安全工学の現状と展望---- 安心社会への安全工学のあり方 ---」とし、①安全工学における安全・安心問題へのアプローチ、②事故調査および責任体制のあり方に関する展望、③社会各分野における安全工学の導入と安全性の評価、④人的ファクターを考慮した安全管理と責任の問題、⑤安全教育の普及方法のあり方と社会倫理の醸成の5項目について提言を行う予定です。私は各論の「化学産業における安全工学と物質安全」の原案を作成しています。ここで、化学産業に係わる安全の課題として、①高機能物質の開発競争激化に対する対応、②自主保安、③ヒューマンエラー対策、④リスクコミュニケーション、⑤テロ、犯罪と危険性物質、⑥遺伝子組み換えによる食料生産の潜在危険、薬害等人が摂取する物質の安全問題の6項目をあげて提言をまとめ、以下の文で締めくくる予定です。「最近の化学産業はファインケミストリーが主流となり、高機能物質の開発競争が熾烈を極めている。そのため、安全確保には化学物質の危険性の迅速かつ適切な把握が重要となっている。化学産業の安全の課題は高機能物質の開発競争激化に対する対応、自主保安に対応するための安全技術の向上と体制の整備、ヒューマンエラー対策、リスクコミュニケーションなどであり、これらの課題を克服するために安全工学が重要な役割を担っている。現在はテロが重大な脅威となっている。爆発性物質、毒物などの危険性物質がテロや犯罪に利用される危険性があるため、危険性物質の管理に関するリスクマネジメントシステムを整備する必要がある。医薬品の安全や食品安全も物質安全の重要な課題である。医薬品では薬害問題、食品安全では残留農薬・動物医薬品による健康影響や遺伝子組み換え食料生産の潜在危険性の問題がある。これらに対して法規制や行政の対応がなされているが、現状では多くの人が不安を抱いている。行政はこの不安を取り除く必要がある。安全工学としては化学物質の安全性や遺伝子組み換えの安全性を確認する評価技術の質を高めることが重要課題である。」
第38号
飯塚義明 <三菱化学㈱>
この原稿は、当方にとって第3作目(4作目?)になります。今回の原稿の締め切りはずっと先かと思っていました。事務局から「明日が締め切りですよ」とメイルを頂き、あせって思いつくまま文字を埋めだしています。
この原稿は、当方にとって第3作目(4作目?)になります。今回の原稿の締め切りはずっと先かと思っていました。事務局から「明日が締め切りですよ」とメイルを頂き、あせって思いつくまま文字を埋めだしています。
年をとると月日の経つのが早くなる。まさか、一日が24時間ではなく、20時間になっている訳ではない。一日の出来事を見聞きした記憶が薄くなるのか、感動がなくなるのか、ともかく、何も残らないで日が暮れ、月曜日から週末まで、あっと言う間に過ぎていく。14年度もあと一月半で終わろうとしています。
三菱化学(旧三菱化成)での社員としての研究生活も残すところ三ヶ月です。その後も会社に残ることで会社と基本的には合意していますが、社内では、「老害」にならないように現役研究者達とは違う分野で安全を見つめていこうと思っています。もちろん、プライベートには、反応暴走はまだ研究を続けようと思っています。
今から30年前、酸化プラントの安全管理のための概念構築と燃焼限界を測定する装置の作成から始まり、反応暴走、粉じん爆発と純然たる化学反応熱の制御が研究の対象でした。
ここ数年、もう少し広義のエネルギー制御と言う観点から、電池の安全に手を出しています。この電池の中は、ミニ化学プラントです。その割には、これまでの電池の安全は、電池メーカーが主体で試験法や基準が決めています。
ご承知のように安全は、絶対論でなく相対論で議論すべきものです。携帯電話のように身体に触れる可能性の高い機器での安全とバックアップ電源としての電池では、ハザードの種類も限界値もおおよそ違うはずです。さらに、最近話題の燃料電池も含め、この「ミニ化学プラント」の安全管理のあり方に手を染めていこうと思っています。
第37号 プロジェクトX 挑戦者たちに思う
西 茂太郎 <練馬区在住>
中島みゆきのテーマソングで始まるNHK「プロジェクトX 挑戦者たち」は私の好んで観る番組の一つである。1月7日に放送された「世界最大の船 火花散る闘い」は、注文主が、私が仕事をしている会社ということもあり、特に身近なものと感じられた。
中島みゆきのテーマソングで始まるNHK「プロジェクトX 挑戦者たち」は私の好んで観る番組の一つである。1月7日に放送された「世界最大の船 火花散る闘い」は、注文主が、私が仕事をしている会社ということもあり、特に身近なものと感じられた。
その船の建造を請け負ったのは、石川島播磨重工業だった。
現場の指揮を託されたのは石川島播磨重工業の技術者、南崎邦夫さん。入社3年目に事故で右足を切断。それでも現場を歩き続けた不屈の男だった。その南崎さんたちの前に次々と難問が立ちはだかる。
最強の鉄板「ハイテンション鋼」。溶接できず真っ二つに折れた。直径7.8メートルのスクリューを支える巨大シャフト。船体に原因不明の歪みが生じ、取り付けられない。
それでも男達は、数々の難問を乗り越えて当時、世界最大のタンカーを完成させた。
司会者の「どうして難問を乗り越えられたのか」の問に対し、南崎さんは「信頼して仕事を任せたからです。信頼されたら、人は最大限、力を発揮するのです」と答えた。
人間は信頼され仕事を任されたら自分の考えで自分のエンジンで動き始めるということは真理だと私は思う。そういうところには後向きの仕事はない。いろいろ困難はあるが建設的な前向きの気持がそこには漂っている。
安全活動も然りではないか。いやいややる安全活動、予定で決まっているからやる行事消化型の安全活動であってはならない。
建設的で創造的な自分達のための安全活動を推進するところには、性質の悪い事故は起こらないしあるいは起こったとしても大事故にはならないのではないか。
安全管理者は建設的で創造的な安全活動の推進に是非力を注いで欲しいと思う。