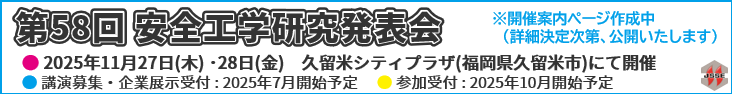セーフティー・はーと
第110号 安全のタテとヨコ
坂下 勲 <坂下安全コンサルタント事務所>
安全を丸ごとでなく,漁網にならって,タテ糸とヨコ糸に分けてみる。
安全を丸ごとでなく,漁網にならって,タテ糸とヨコ糸に分けてみる。
タテ糸は,安全法規・技術情報・事故事例あるいは企業倫理など,安全の構造を支える分野。まとめて,「標準安全」と呼ぶことにしよう。本来は,経営や本社の管理部門が担当する事項である。
一方,ヨコ糸は,安全教育・作業マニュアル・品質管理・設備保全など,危険と直接向かいあっている現場での具体的な安全実務で,「個別安全」と呼ぶことにする。このタテ・ヨコは適宜決めればよい。
ところで,もし魚網が,タテ糸だけだったらどうだろう。糸がぶらぶらして,すきまが開いてしまうため,魚を捕まえるのは難しくなる。ここに,一本のヨコ糸が絡んでくると,タテ糸は拡がることなく,魚を捕えられる。ヨコ糸の本数をもっと多くして網にすれば,十分に機能を発揮できる。相互補完による両機能の向上効果である。
安全でも同様に,「標準安全」と「個別安全」の双方の糸が相互にしっかりと連携補完しあって,はじめて期待される安全が実現される。
コンプライアンスとか企業倫理とかの,難しそうな話は,総じてタテ糸・「標準安全」に属する問題が多い。危険に直接向かい合っていないスタッフが担当しているせいか,対応が抽象的・精神論的に偏り,抜けや落ちが発生し易い。
一方,危険と直接向かい合っている現場では,さぞ毎日緊張しているかと思いきや,設備の高性能化や自動化が進んで危険が直接見えなくなり本社サイドと同様,とくにヒューマンファクタの問題を多く抱えている。
タテ・ヨコの安全の糸がうまく絡み合った相乗効果の発揮,そのための安全教育の充実が期待されるゆえんである。
安全文化。いろいろな言い回しがあるようだが,タテ糸とヨコ糸が華麗に織りなす織布の縞や絵柄の模様に例えると解り易いかも。模様がその企業独自のものであれば,本物の安全文化であろう。
マスコミ報道される不祥事や事故トラブルの類も,タテ糸とヨコ糸に分けて眺めて見ると,少しは問題の核心が見えてくるのではないだろうか。